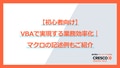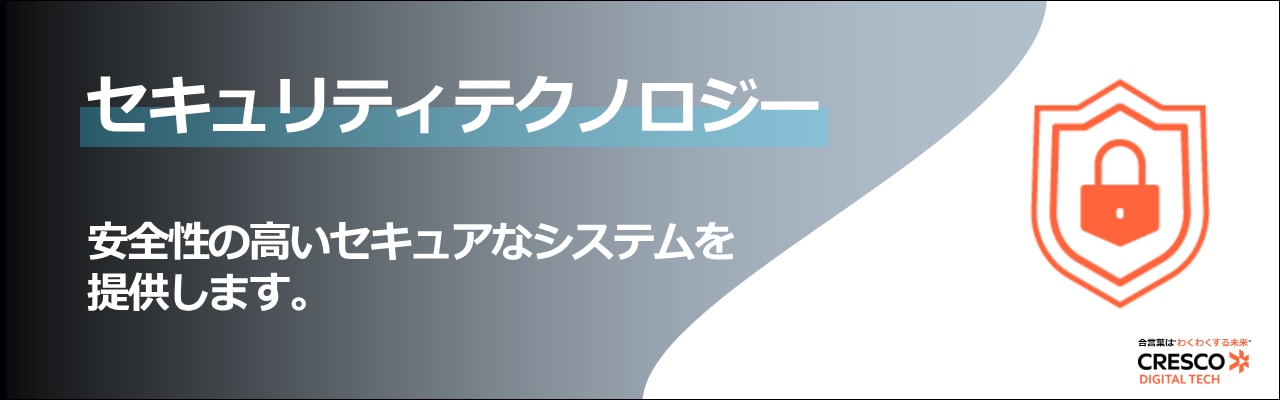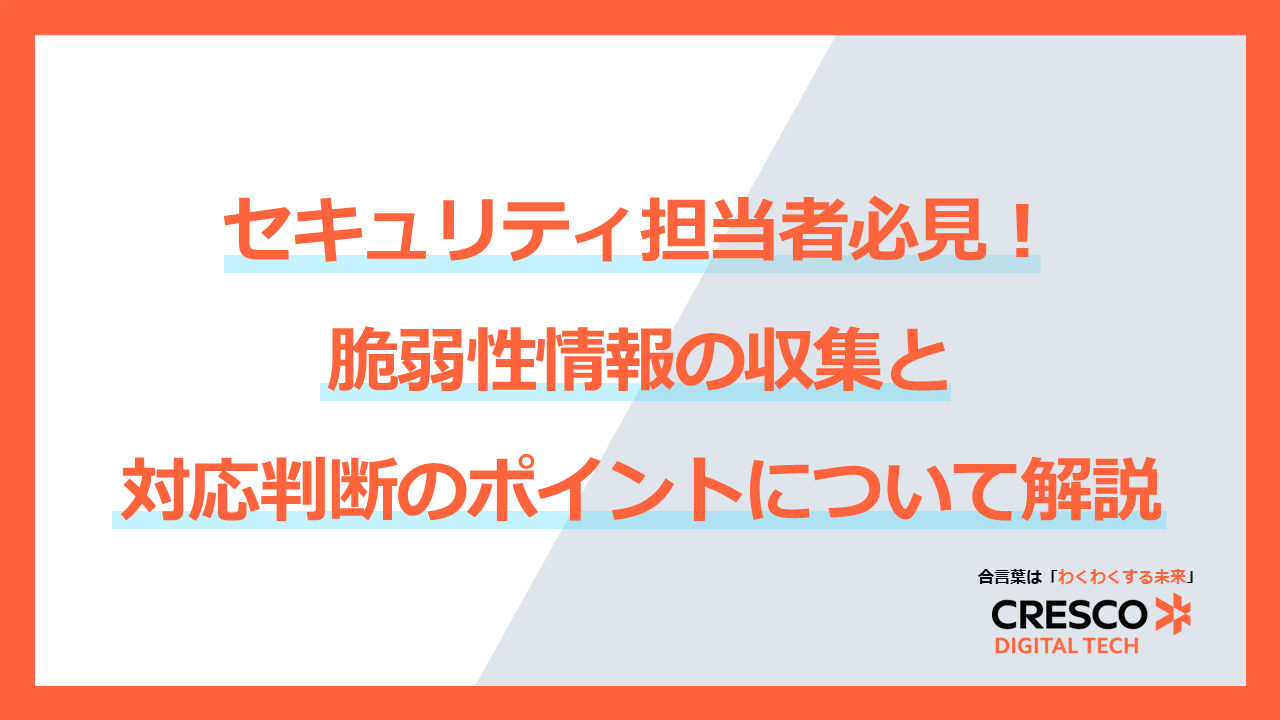
セキュリティ担当者必見!脆弱性情報の収集と対応判断のポイントについて解説
こんにちは、クレスコ・デジタルテクノロジーズのWeDです。
「脆弱性情報の収集」をテーマに、その方法と重要性について解説します。
多くの組織では、脆弱性情報の収集が担当者任せになっていたり、収集した情報をどのように活用すべきか、適切な判断を下すことが難しいという課題を抱えています。
本記事では、こうした課題に対する具体的な解決策として、効果的な脆弱性情報の収集方法と活用のポイントを解説します。
サイバー攻撃から企業の資産を守るための基本的な対策として、少しでも参考になれば幸いです!
■あわせて読まれている資料:
対応事例やセキュリティサービス一覧を掲載!
→セキュリティテクノロジーサービス
目次[非表示]
- 1.脆弱性情報収集が必要な理由と背景
- 2.脆弱性情報の収集ルートと信頼性の高い情報源
- 3.情報の活かし方と判断のポイント
- 4.継続的な収集体制の重要性
- 5.弊社サービス紹介
- 6.まとめ
- 7.引用元
脆弱性情報収集が必要な理由と背景
近年、サイバー攻撃の手口はますます巧妙化・高度化しており、多くの製品ベンダーが日々新たな脆弱性の存在を公表しています。
中にはすでに攻撃に悪用された事例が報告されているものも含まれており、そうした情報を把握していないことが重大な被害につながるおそれもあります。
このような背景から、組織が優先して取り組むべきセキュリティ対策の一つとして、「脆弱性情報の収集」は欠かせないものとなっています。
脆弱性情報の収集ルートと信頼性の高い情報源
脆弱性情報を収集する上で最も重要なのは「信頼性の高い情報を継続的に取得できる体制を確保すること」です。
まず、最も基本的かつ確実な情報源は、製品ベンダーの公式サイトです。多くのベンダーは自社製品に関する脆弱性情報を公式サイト上で随時公開しているため、まずはこちらを参照するのがよいでしょう。
加えて公的な脆弱性データベースの活用も有効です。代表的な例としては「CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)」が挙げられます。
これは、米国政府の支援のもと脆弱性に一意の識別番号を付与して管理しているもので、正確な情報を得る手段として非常に有用です。
その他、セキュリティ関連のブログやSNSなどから情報を得ることも可能ですが、信頼性や継続性の観点からあくまで補助的な情報源と位置づけるべきでしょう。
情報の活かし方と判断のポイント
収集した情報を有効に活用するためには、「自社にとって対応が必要かどうか」を的確に判断することが求められます。情報はただ多く集めればよいというものではなく、整理・分類して“使える形”にすることが重要です。
まず確認するべきは、自社の環境がその脆弱性の影響を受けるかどうかです。
たとえば、対象の製品やバージョンを現在利用しているか、問題となる機能や設定が有効になっているか、当該サービスが外部公開されているかといった点を確認します。
そのためには、あらかじめ社内IT資産を正確に把握・管理しておくことが不可欠です。
表1.脆弱性影響判定リスト
判断項目 |
チェック内容 |
対象製品の利用有無 |
該当製品・バージョンを使用しているか |
該当機能の有効化状況 |
問題となる機能や設定が有効になっているか |
公開状況 |
該当製品が外部ネットワークに公開されているか |
攻撃事例の有無 |
実際に悪用された報告があるか |
パッチの提供状況 |
ベンダーから修正パッチが提供されているか |
自社の対応状況 |
バージョンアップ、パッチ適用などの緩和策を実施済みか |
また、脆弱性の中にはすでに攻撃に利用されているものもあります。
セキュリティベンダー等から攻撃事例が報告されている場合、CVSS(共通脆弱性評価システム)のスコアにかかわらず迅速な対応が求められるケースもあります。
情報を実際の対応に繋げるためには、組織としての対応方針や判断基準を明文化しておくことが望まれます。たとえば、「CVSSスコアが7.0以上かつ外部公開サーバに影響する場合は、3日以内にパッチを適用する」といった基準を設けておくことで属人的な対応を避け、対応の迅速化にもつながります。
一方で、パッチが未提供であったり、システムの都合により適用が困難な場合もあります。
そういった場合は、アクセス制限や対象機能の一時停止などの回避策を講じ、リスクを最小限に抑えることが求められます。
状況に応じて柔軟に対応できるような制度を整えておくことが重要です。
このように、単に情報を集めるだけでなく自社のシステム構成や運用状況、セキュリティポリシーに照らして対応を適切に判断することが求められます。
継続的な収集体制の重要性
脆弱性情報の収集と対応は、一度きりで完結するものではありません。
日々新たな脆弱性が公表され、攻撃手法も進化し続けています。昨日まで安全だった環境が今日には新たなリスクを抱える可能性もあります。
そのため、「定期的に確認する」といった対応では不十分です。情報収集は「継続的かつ組織的」に行う必要があります。
具体的には、自社で利用している製品やサービスの情報と脆弱性情報とを紐づけ「自社に影響があるかどうか」をすぐに判断できる体制を整えることが重要です。
弊社サービス紹介
上記のように、脆弱性情報の収集はその重要性に反して非常に煩雑で手間のかかるものでもあります。
そこで弊社では、毎月ご指定の製品やOSについて脆弱性情報を集約し結果をご報告する、脆弱性情報提供サービスを提供しています。
お客様のネットワーク環境・ご利用機能・設定情報などを基に、脆弱性が現環境に影響を及ぼすものかどうかを分析・評価するオプションも提供しており、継続的なセキュリティ対策の実現に大きく貢献できるサービスとなっておりますので、ぜひご検討ください。
■詳細はこちら↓
まとめ
脆弱性情報の収集は単発の作業ではなく、組織として継続的に取り組むべき“防御の第一歩”です。
正確な情報を信頼できるルートから継続的に集め、迅速かつ的確な判断につなげることが、サイバーリスクを最小限に抑える鍵となります。
「知らなかった」では済まされない時代において、継続的な情報収集こそがサイバーリスクを最小限に抑えるための最も基本かつ重要な対策であると言えるでしょう。
■サービス資料一覧はこちら↓